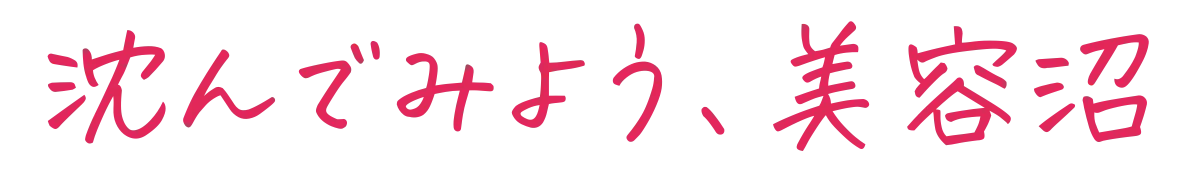美容系の情報を収集できるSNSでは「美容皮膚科で働いてる友人ナースがマジでオススメしてた〇〇、ニキビが2日で消えたんだけどヤバくない?」のような投稿がバズりやすいです。
バズった投稿は多くの人から興味関心を寄せられるため、投稿文だけを見て購入する人も少なくありません。
では、SNSやブログの投稿は何処まで表現していいのでしょうか。実は、SNSやブログなどの投稿や販促用LP・バナーなどで表現して良い範囲は、薬機法と呼ばれる法律により定義されています。
薬機法では、簡単に言うと「薬機法が定義する広告に該当する場合は、化粧品も含む医薬品等の効能・効果を医薬品や医療行為に誤認するような表現を文章や画像で使ってはいけない」のように広告を規制している法律です。
本記事では、SNSやWEBサイト、LPなど薬機法で表現が規制されている広告は、何がどのように規制されているのかを解説します。
そもそも薬機法って何が広告に該当するの?
「広告」と聞くとアフィリエイト広告やSNS広告を想像するかもしれませんが、薬機法では店舗のWEBサイト(ホームページ)やGoogleビジネスプロフィール、SNS、商品販売のLPなども広告に該当する場合が多いです。
まずは、どのようなものが薬機法上で広告と定義されているのかを抑えていきましょう。
薬機法での広告定義は「誘引性」・「特定性」・「認知性」を満たすもの
薬機法の定義において、広告は「誘引性」・「特定性」・「認知性」の3要件を満たすものと定められています。言い方を変えると、薬機法ではこの3要件のうち1つでも欠けている場合は広告に該当しません。
- 誘引性:商品やサービスを買って欲しい・使って欲しいという狙いがある
- 特定性:商品名やブランド名、サービス名、店舗名がハッキリ表示されている
- 認知性:SNSやブログ、店頭チラシなど誰でも不特定多数が見れる
この3要件が揃ったものは紙でもインターネットの情報でも、すべて薬機法の定義における広告に該当します。具体的には、以下のような表現をイメージしてください。
- 「お試し1,000円!ハイクラス施術がこの価格♡」
- 「無料カウンセリング受付中!ぜひ体験してみて!」
- 「期間限定・先着50名様!特別プラン♡」
- 「当日予約OK★今すぐ連絡!」
- 「〇〇スリムコースで脚痩せ♡」
- 「“〇〇”ブランドのアロマオイルで極上マッサージ」
- 「美白美容液『ホワイトパワーEX』を使ったフェイシャル」
- 「医薬部外品『スキンケアエッセンスNo.11』が新発売!」
- 割引情報やキャンペーン、購入リンクの貼り付けなどはわかりやすい“誘因”なので要注意。
- URLやリンク先がその商品の公式販売ページだったり、テキストリンクに商品名が入っている場合も要注意が必要
- 鍵付きアカウントや限定コミュニティでも、実質的に簡単に参加できる場合は認知性があると判断されるケースもある。
美容・健康系の広告表現は薬機法で規制されている
薬機法の目的は簡単に言うと、健康の観点から危険な可能性がある医薬品などを規制したり、逆に必要な新薬や医療機器の開発を支援したりすることで、私たちの健康を守ることです。
この目的に従い、薬機法ではWEBサイトやSNSなどを含むすべての広告で以下のような広告展開を禁止しています。
- 医薬品等の効能や効果、性能に関する虚偽・誇大広告や、医師や専門機関などが保証したと誤解されるおそれのある広告は禁止。
- 特定疾病の治療薬については、医師や薬剤師などの医薬関係者を対象にした広告に限って認めており、一般人を対象にした広告してはいけない。
- 承認を受けていない医薬品等の名称、製造方法、効能、効果、性能に関する広告してはいけない。
なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、エステサロンのWEBサイトや化粧品・サプリメントの販促用LPなどは扱っている化粧品や美容機器などが医療的なものと誤認されないように注意が必要だと覚えておきましょう。
薬機法は企業・店舗・個人すべての人が守るべき法律
広告表現について規制している薬機法の第66条・68条では、「何人も~~~~してはならない」と記載されています。
- 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
- 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
- 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
この「何人」には例外がありません。企業や店舗などの団体はもちろん、私たち一個人まで、全員が等しく薬機法を守る義務があります。
また、禁止されている広告を扱っている中心人物・団体が指定されていないことにも注意しましょう。事件で言うところの「主犯」が誰かは問われていない状態です。
そのため、広告を展開している大元の会社や店舗だけではなく、その広告を使用して販促を行っている販売業者や、広告を掲載したメディア、広告を作成した広告代理店、制作会社、下請けのデザイナー、広告の記事やキャッチコピーを書いたライター、SNSのインフルエンサーなども処罰対象となる可能性があります。
薬機法違反は匿名で通報できるため、いつ誰から通報されるかわかりません。誰に見られても薬機法の観点で問題ない広告になるよう、表現には注意しましょう。
LPやバナー、SNSなど広告で扱って良い「医薬品等」の定義
薬機法の目的を解説する上で「医薬品等」という表現が出てきました。
「医薬品等」の定義には、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の5つが含まれます。
- 医薬品:病気の予防や治療、診断を目的に処方される、体の機能などに影響を与えるもの
- 医薬部外品:医薬品のような改善・治癒効果はないけど、予防効果が期待できるもの
- 化粧品:お肌のうるおいを補充したり、なめらかにしたりするためのもの
- 医療機器:人や動物の病気の診断や治療、予防に使う器具や装置など
- 再生医療等製品:先端医療として注目されている、遺伝子治療などに使われるもの
薬機法上の広告では、これら5つがそれぞれで認められた効能・効果を超えるような表現を行わないよう、注意が必要です。
たとえば、化粧品なのに医薬品と誤認される可能性がある表現は使用してはいけません。
では、実際どのような点に注意すれば良いのかを解説します。
医薬品等の定義に含まれるもの①医薬品
医薬品は、次の3つのどれかに該当するものと定義されています。
- 日本薬局方に収められているもの
- 「日本薬局方」は公的な薬の基準書の名前。
- 要は「これは医薬品」という基準書に書かれているものは医薬品に該当する。
- 例:「○○成分は日本薬局方に入ってる」→この場合は化粧品や食品ではなく医薬品の枠。
- 人・動物の疾病診断等に使用することが目的であるもの
- 痛み止めやワクチン、抗生物質など人・動物の病気を治療・予防するためのものは医薬品。
- 形状が「機械器具等ではないもの」と指定されているため、注射器や血圧計は医薬品ではなく医療機器。
- この場合、注射器の中にある薬液は医薬品。
- 人・動物の身体の構造などに影響を及ぼす目的があるもの
- ホルモン剤や成長因子など、体の構造や機能に変化・影響を与えるための物質も医薬品に該当することがある。
- 種類として「医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品ではないもの」と定義されている。
- 体に変化・影響を与えつつ上記に該当しないものであるため、化粧品などよりも体への影響が強いものとイメージすると良い。

化粧品や医薬部外品、医療機器、再生医療等製品の広告をする際は
「医薬品」と誤認しないよう注意が必要です。
医薬品等の定義に含まれるもの②化粧品



本来は先に医薬部外品を紹介する流れなのですが、
先に化粧品の定義を把握しておいた方が
スムーズなため先に解説します!
薬機法において、化粧品は以下のように定義されています。
第二条第三項
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
つまり化粧品の定義は簡単に言うと、以下を満たすものだと考えてください。
- 人の体を清潔に保ったり美しくしたりするため、
- もしくは皮膚か毛髪を健康的な状態に保つために
- 体に塗り広げたりスプレー等でまき散らしたりなどの方法で使う
- 医薬品のように効果が強くなく、軽い(緩和)なもの
この定義だけを見ると簡単なように感じるかもしれませんが、化粧品を広告する際はこの定義から飛び出すのはNGです。
化粧品は、以下の画像に記載されている効能効果以外を広告してはいけません。




化粧品の広告表現は、その良さを伝えようとするあまり、医薬品や医薬部外品のように広告して薬機法違反になりがちです。
具体例を挙げると、「毛穴がなくなる」「ニキビを改善する」のように、医薬品と同等の効果がある化粧品のように広告してしまうケースがあります。
化粧品はあくまで体を清潔に保ったり美しくしたりすることが目的であり、化粧品の広告で病気や症状の治療効果は認められていません。
そのため、たとえば「できたてニキビに効く」のように美容液のPRをしてしまうと、その美容液は薬機法上、化粧品ではなく医薬品として扱われます。
しかし、医薬品は承認を受けたもの以外は広告できません。
そのため、「できたてニキビに効く美容液」と表現した広告は、化粧品ではなく未承認の医薬品を広告したことで薬機法に違反したと見なされます。
また、医薬部外品として認められている場合を除き、本当に効果があったとしても、化粧品の分類である限りは予防効果なども表現できません。



化粧品の広告をする際は、「ケア」「サポート」「肌を整える」など、医薬品と誤認されにくい表現を使うことを意識しましょう!
医薬品等の定義に含まれるもの③医薬部外品
医薬部外品の定義に含まれるものは、体に対する作用が医薬品よりも効果が軽く(緩和)で、吐き気や口臭、あせもやかぶれなどを防ぐものです。
具体的には、使用目的が以下のどれかに該当する場合は医薬部外品に含まれます。
- 吐き気やその他の不快感、口臭、体臭の防止
- あせも、ただれ等の防止
- 髪の毛や体毛などに関する脱毛の防止や育毛、除毛
ただし、医薬部外品の中には「指定医薬部外品」として承認された場合は、上記以外に指定された効能・効果を広告可能です。
化粧品で「医薬部外品」として販売されている商品の大半は指定医薬部外品として承認を受けており、薬用化粧品と呼ばれることもあります。
医薬部外品として指定を受けた薬用化粧品は、化粧品としての効能にプラスして、以下の画像のような効能・効果を広告しても問題ありません。


医薬品等の定義に含まれるもの:医療機器・再生医療等製品・その他について
医療機器や再生医療等製品は取り上げる物によって分類が非常に細かいため、ここではよくエステサロンやリラクゼーションの広告で見るNG広告例を見てみましょう。
- レーザー式脱毛機器は医療機器に該当するため、医師免許保有者がいないエステサロン・脱毛サロンで扱うのはNG
- HIFUと呼ばれる肌のたるみやハリ改善に効果があるものも医療機器であるため、エステサロン等の広告で扱ってはいけない。
- 一般的に美顔器は医療機器ではなく「雑品」として扱われるため、薬機法としての規制はない。
- ただし、医療機器のように身体の構造や機能に影響を与えるような広告表現はNG。
- 「肌にうるおいを与える」のような化粧品効果を標榜する場合はエビデンスが必要。
- NG例:
- 低周波による皮下の新陳代謝の活性化
- ほうれい線を薄くする
- 医療機器と同様の機能で安全
- 顔の脂肪を分解
- アクネ菌への殺菌効果でニキビケアに最適
- 美肌成分をイオンとして肌の深部に送り込み、電気の力で浸透させます。
- EMSは薬機法で「雑貨」として扱われるため、美顔器と同様に薬機法としての規制はなし。
- ただし、「30分つけるだけで痩せる」のように、体の変化を謳うような広告は医療機器扱いになってしまうためNG
- 「ヒト幹細胞」は再生医療等製品の定義に該当するため、化粧品として広告してはいけない。
- 製造過程で幹細胞を培養する際に分泌された「ヒト幹細胞培養液」はOK。
- ただし、ヒト幹細胞培養液を使った化粧品を「ヒト幹細胞美容液」のように表現するのは誇大広告なのでNG。
- あくまで「ヒト幹細胞」ではなく「培養液」を使用していることを明言することが重要。
- ただし「ヒト幹細胞培養〇〇」であっても「幹細胞にアプローチ」「肌細胞を再生/活性化」のような表現やNG。
ネット上の媒体はどんなものが広告に該当する?
WEBサイトやGoogleビジネスプロフィールのような店舗名・サービス・料金・予約方法などを展開している媒体は、「誘引性」「特定性」「認知性」の3つが揃っていると認識されるため、広告の定義に該当しやすいです。
基本的には「来店してほしい」「商品を買ってほしい」など、販売・利用を促す狙いがあるものは広告だと考えましょう。
薬機法上の広告に該当する場合は、使用する文言は以下のようなポイントに注意して作成する必要があります。
- 確実に効果を保証できないものなどは誇大表現、虚偽表現になる可能性があるのでNG。
- 化粧品や医薬部外品を医薬品や医療機器と誤認させるような表現を使わない
- 化粧品や医薬部外品は定められている広告OKな表現範囲を逸脱しない。
とはいっても、実際にどのような表現が薬機法違反になるのかピンとこない方も多いでしょう。
以下では、どのような広告が薬機法違反に該当するのか、具体例を紹介します。
WEBサイト(ホームページ)・LPが薬機法違反になる事例
WEBサイトの薬機法違反でありがちなのは、提供する施術や施術に使用するものを医療行為・医薬品・医療機器のように表現してしまうケースです。



医療行為を扱って良いのは医師のみです!
体の構造や機能に変化を与えるようなサービスや商品は「医薬品」「医療機器」に該当します。2つ以外のもので体の変化を謳った広告は薬機法違反となるため、注意しましょう!
WEBサイトでよく違反事例として見かけるのは、サービスや施術中に使用する化粧品の効能などを表現する際に「免疫」「細胞」「改善」「活性化」「予防」のような言葉を使っているケースです。
美容系サービスを扱う店舗のWEBサイトにありがちな薬機法NG表現例
たとえば、エステサロンやリラクゼーションサロンなど、美容系サービスを扱う店舗のWEBサイトに使われがちなNG表現は以下のようなものがあります。
- 「しっかりと行う腸もみで不要物や毒素を排出!デトックスサポートはお任せください。」
- 「〇〇(美容成分名)をお肌の奥まで浸透させます。」
- 「△△美容機器を導入!脂肪細胞を破壊してスッキリボディへ。」
- 「ヒト幹細胞を培養した美容液を使い、お肌の細胞をより若々しい状態へ活性化いたします。」
- 「アロマの効果で免疫アップ!風邪や花粉症の予防としてもオススメです。」
- 「オールハンドの施術でお肌を引き上げリフトアップ!アンチエイジングで-10歳肌へ。」
- 「むくんだふくらはぎや腰をほぐし、血行や辛い体の疲れを改善いたします。」
- 「アンチエイジングなら当店の〇〇をご利用ください。」
販売促進用のLP(ランディングページ)やバナー画像
サプリメントや化粧品の販促用LPや広告に使うバナー画像の薬機法違反の多くは、販売しているものが医薬品ではないにもかかわらず「免疫」「細胞」「改善」「活性化」「除去」のような表現を使い、まるで医薬品のように広告してしまうケースです。
化粧品やサプリメントは「人体に対する作用が緩やかなもの」であるため、たとえば「~~を根本から改善」のような、医療行為・医薬品と誤認させるような表現を使ってはいけません。
また、LPやバナーの表現は、自社データや体験談が信頼性に欠けるパターンも多く見受けられます。
「モニター全員が1週間で×kg痩せた」のように、明らかに信用できない数字や事例を押し出すと薬機法違反に抵触する可能性が少なくありません。
もちろん、信頼できる第三者データやきちんとした客観的エビデンスがあれば別です。しかし、裏付けや根拠が不十分だと虚偽表現や誇大表現と見なされてしまうため、注意しましょう。
加えて、「〇〇学会が絶賛!」「〇〇クリニックで使用中」「専門医が注目」のような表現もNGです。
薬機法では、医療関係者や美容師(理容師)、病院(診療所)、学会など、権威性を持つ人・団体による推薦とみなされるような表現は禁止されています。
これは大学や学会、医師などの名前を出すことで「医学的に立証されているんだ!」と消費者が誤認しやすいため、大学・研究機関名などを出すことで誤解を与えないための規制です。
化粧品やサプリメントなど商品の種類は問わず、医療関係者などの推薦と感じるような表現により、医薬品的効能を連想させる広告は薬機法に抵触します。
なお、「〇〇大学と共同研究」のような表現にも注意してください。
医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)では、「医薬関係者等の推せんに抵触するため、「大学との共同研究」と記載は認められない。」とあります。
「大学との共同研究」という表現が医薬関係者の推奨表現に引っかかる場合や、その表現により医薬品レベルの効能を広告していると判断された場合は薬機法違反です。
事実であっても、「〇〇と共同開発/共同研究」のような表現は使わず、医薬品に見えないよう表現を調整しましょう。
LPやバナー画像にありがちな薬機法NG表現例
- 「100 %無添加」:何を含んでいないのかを示せばOK
- 「肌に潤いを与える」など配合目的を記載しない状態での「〇〇配合の~~~」のような表現。
- 「一日中こんなに潤いました。」のような表現:肌が乾燥している状態のビフォーと潤っている状態のアフターを示しても、効果を暗示するためNG
- 「あの人気芸能人〇〇も使っています」:彼らが製品の効能を過度に称賛する発言をすると違反
- 体験談「私も使ってます」や「感謝しています」など:「◯◯を飲んだら血糖値が下がりました!」のように具体的な内容を記載していなくともNG
- 「塗るだけでシミが消える美容クリーム」:医薬部外品として承認されていれば可
- 「業界No.1の痩身効果を実現!」:客観的根拠無しでの広告は誇張表現に該当
- 「特許取得済みの新成分配合!」:特許そのものは事実でも、宣伝に用いると公的なお墨付きのように誤認されるためNG
- 「医薬品と同じ成分配合」:製品が医薬品と同等の効能があるかのように思わせるためNG
- 「朝夕2回の服用を、効果を高めるため3回に増やしてもOK!」
Googleビジネスプロフィール(Googleマップ情報)
「渋谷 居酒屋」のように検索すると、おすすめ店舗のGoogleマップ情報が表示されますよね。各店舗ごとの登録情報は「Googleビジネスプロフィール」と呼ばれています。
意外と忘れがちなのですが、このGoogleビジネスプロフィールも薬機法上の広告に該当しやすいです。
具体的には、以下のような運用を行っている際は広告に該当します。
- 誘引性:利用促進のため店舗のアピールポイントの明記や投稿・画像をアップしている状態。
- 特定性:店舗名やサービス名、料金など商品名やブランド名、サービス名、店舗名がハッキリ表示されている状態。
- 認知性:Googleビジネスプロフィールは公開状態なら誰でも自由に閲覧可能。
GoogleビジネスプロフィールはMEOと呼ばれるアルゴリズムで上位表示が左右されるため、上位表示を目指してアルゴリズムに適した情報を登録・投稿・更新する方がほとんどです。
私が今までMEOに携わった中では、傾向としてエステサロン・マッサージ店・リラクゼーションサロン・脱毛サロンは登録情報や投稿内容が法令に違反しているケースが多く見受けられました。
GoogleビジネスプロフィールもWEBサイトやLPと同様に、薬機法の表現規制対象です。
WEBサイトやLPでNGな表現例は、Googleビジネスプロフィールでも規制されていることを覚えておきましょう!
Googleビジネスプロフィールは、特にラフなノリで更新しがちな投稿機能や、投稿された口コミに注意が必要です。
投稿機能はWEBサイトやLPと同様の規制に注意すれば問題ありませんが、「ぎっくり腰に悩まされていましたが、ここで施術を受けたら治りました!」のような過剰に医療効果をイメージさせる口コミをそのまま放置しておくと、口コミも広告と見なされる場合があります。



「口コミなんて自分が投稿した訳じゃないのに!」とは思いますよね。
そのため、医療行為を想像させるような口コミが投稿されたら、「当店は医療機関ではないため治療は行っておりませんが~~~」のように返信するなど、工夫するのがベターです。
GBPにありがちな薬機法NG表現例
- 「当店の〇〇は女性ホルモンや自律神経を整える効果がございます!」
- 「〇〇(施術名)は、生理痛や更年期障害になど女性ならではのお悩みを抱える方におすすめです!」
- 「〇〇(美容機器名)は、脂肪と老廃物が結びついて固くなってしまったセルライトやむくみの除去に効果的!ダイエットしたいけど続かない方はぜひ【リンク】よりご予約ください♪」
- 「急に寒くなり、全身のだるさや疲労感や手足の冷え、むくみが気になりませんか?」
- 【口コミ】「ここで〇〇(施術名)を受けたら△△(病気・疾患名)が治りました!」
- 【口コミ】「リラクゼーションの域を超え、しっかりとした技術で体の不調を改善して頂きました。」
- 【口コミ】「合わなくて行くのをやめた〇〇(競合店名)より施術が良かった!」
メルマガ、LINE公式アカウントの配信
「メルマガやLINE公式アカウントは登録が必要だから、誰でも閲覧できる状態ではないのでは?」
こう思う方は多いですが、メルマガやLINE公式アカウントで行う発信も広告に該当します。
認知性は「誰でも閲覧できる状態」と説明しましたが、これは言い換えると「不特定多数または多数の人が閲覧・認知できる状態」とも解釈可能です。
メルマガやLINE公式アカウントは確かに登録が必要ですが、受付条件が「誰でも大歓迎」のように緩く、特に厳しい審査なく申し込みできる状態であることがほとんどですよね。
このような場合は、事実上不特定多数が閲覧できる状態と判断されやすいです。
会員制サロンや利用者限定の配信、有料コミュニティなど、限定的なメンバーへの配信であれば「不特定多数が閲覧できる状態」とは言い切れません。
しかし、企業や店舗が配信するメルマガ・LINE公式アカウントは、基本的に多くの人に登録してもらいたいものです。そのため、実質「多数が閲覧できる状態」とみなされやすいと考えましょう。
SNSやブログへの投稿
薬機法の規制はすべての人を対象としているため、個人が運用しているSNSやブログでも、広告に該当する場合は薬機法違反のリスクがあります。
Amazonや楽天、その他ASP経由も含め、アフィリエイト広告のリンクを貼っている場合は薬機法上の広告に該当しやすいです。
- 誘引性:「この商品最高だからみんな買って!」のように記載している。
- 特定性:商品名やブランド名のほか、広告リンクや企業から指定されたリンクを記載している。
- 認知性:非公開状態に設定していなければ誰でも閲覧できる状態。



逆にアフィリエイトなし&ただの体験記で「勧誘要素ゼロ」の投稿なら薬機法上は広告ではないと判断されることも多いです。
特に注意が必要なのは、フォロワーが多いインフルエンサーや広告収入を目的に発信するアフィリエイターです。
実際、2021年には自営業の男性がアフィリエイト広告における薬機法違反で書類送検されています。
この事例は当人のサイトでサプリメントに関する説明として「更年期障害・糖尿病・痛風の予防・改善に効く」などと表示して販売・販促を行い、このサイトでは3個しか売れていないにも関わらず摘発されました。
薬機法の広告規制は販売実績や規模を問わず、企業・店舗・個人を問わずすべての人を摘発対象としています。
SNSではモニターPR案件として化粧品会社から頼まれてレビューを投稿する方もいますが、このような「紹介」であっても企業から依頼されて書いているものは広告と扱われることが多いため、投稿内の表現には注意してください。
また、SNSへの投稿は誇張表現に該当する文章が違反しがちです。
後述にあるようなバズり目的での表現は薬機法に抵触するリスクが高いため、使用する際は内容を精査した上での投稿をおすすめします。
なお、薬機法の規制対象には文字だけではなく、画像や動画も含むことも覚えておきましょう。
SNSにありがちな薬機法NG表現例
- 「これマジで〇〇(ニキビ等)の特効薬過ぎる」
- 「美容クリニックのナース(の友人)が『~~~』ってオススメと噂の〇〇」
- 「~は美容皮膚科の常識」
- 「クリニックの~~でも人気で最近よく聞く成分だけど……」
- 「これ使っただけで毛穴が消えた」
- 「脂性肌でこれを使わない理由はない」
- 「ニキビ美白毛穴とか全部に効く」
- 「これを使い出してから皮脂が減ってニキビ地獄から解放された」
- 「医療より毎日のスキンケアでこれを使う方が良い」
- 「乾燥+赤ら顔+花粉症で毎年死んでるんだけど、この組み合わせで悩みが一瞬で解決した」
- 「皮膚科でさじを投げられた私が~~~」
美容情報を扱う際は薬機法に違反しないように注意しよう
本記事でご紹介した内容の中でも、特に5つのポイントについては抑えておきましょう。
- 薬機法では「誘引性」・「特定性」・「認知性」の3つを満たすものはすべて広告に該当する。
- 薬機法の規制対象は医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品に関する広告表現。
- 化粧品・医薬部外品の広告を作成する時は、承認されている効能・効果の範囲を超えてはいけない。
- 化粧品や医薬部外品を「医薬品・医療機器・再生医療等製品」と誤認させる可能性がある、極端な表現や嘘を広告に含んではいけない。
- もし化粧品や医薬部外品を医薬品に誤認させるような広告を出した場合、承認無しで医薬品を販売したと見なされ、薬機法違反として扱われる。
インターネット上で良く見かけるWEBサイトやLP、バナーなどは、条件を満たしている場合はすべて薬機法で定義されている「広告」として扱われます。
「広告」の定義に該当するものは、企業や店舗だけではなく、インフルエンサーやブロガーなどまで等しく、薬機法に違反しないように注意しましょう。
また、薬機法違反を発見した場合は、誰でも匿名で厚生労働省のページから通報できます。
特にサプリメントや化粧品(コスメ)に関する広告を扱う場合、誰から通報されてもおかしくありません。
「この人の投稿は通報した方が良いのでは……?」と思われないよう、インターネットに広告を投稿する際は表現に注意し、誤解が生じない適切な情報を発信しましょう。